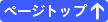患者の皆様へ
薬剤部からのご案内
入院される際のお薬の持参について
入院時には薬剤師がお薬の確認をしております。
入院される際には以下の事項にご協力ください。
- 現在、使用中のお薬のみ、必要量をご持参ください。
(必要のないお薬は、お持ち帰りいただく場合がございます) - お薬手帳やお薬の説明書をお持ちでしたら、併せてご持参ください。
お薬に関する説明や相談について(入院中の患者さん)
各病棟の担当薬剤師がベッドサイドまで伺い、お薬の説明をいたします。
薬剤師が伺う時以外でもお薬のことで相談したいことがあれば、いつでも病棟スタッフに声をお掛けください。
お薬に関する説明や相談について(外来通院中の患者さん)
1号館1階に「お薬相談室」がございます。
- 開院日
- 8:45 ~ 16:30
おくすりの正しいのみ方について
お薬をのむ時間について
主なのみ方は次の通りです。
- 食直前
- 食事の直前
- 食前
- 食事の20~30分前
- 食後
- 食事の後20~30分以内
- 食間
- 食事と食事の間で、食後2時間ごろ
- 就寝前
- 寝る直前または30~60分前
- 頓服(とんぷく)
- その症状が出たとき(例えば発熱時や頭痛時など)
お薬は水やぬるま湯と一緒にのみましょう
- お薬はコップ1杯(約200cc)程度の水またはぬるま湯でのみましょう。
水分制限のある方は医師の指示に従ってください。 - 少量の水もしくは水なしでのむと、十分な効果が発揮できないことや、お薬によってはのどや食道にくっついて粘膜をいためることもありますので、ご注意ください。
- お水以外の飲み物でのむと効果が弱まったり強まったりすることがあります。
お薬をのみ忘れたときは?
- 基本的には、次にのむまでの時間があいていれば、気付いた時点でのんでください。
- 次にのむ時間が迫っているときは、1回分はとばして次回分のお薬をのんでください。
- 一度に2回分をのんではいけません。お薬の副作用が出ることが考えられます。
- 服用間隔の目安は、1日3回のお薬なら4時間以上、1日2回なら6時間以上はあけるようにしましょう。
- 糖尿病のお薬など、対応が異なるお薬もあります。不明な点は医師または薬剤師におたずねください。
お薬と食事について
多くのお薬は「食後」の服用になっています。それはのみ忘れを防ぐために食事と関連付けているためです。
しかし、食欲がなくて食事をとれない時や検査などで食事をとばさなければいけない時があります。糖尿病のお薬など食事と密接な関係があるお薬もありますので、勝手に服用をやめたりせず事前に医師または薬剤師におたずねください。
おくすりQ&A
お薬手帳ってどんなもの?
- お薬手帳とは、いつ、どこで、どんな薬を処方してもらったかを記録しておく手帳のことです。
- お薬手帳のメリットは?
かかりつけでない病院、薬局にかかる場合でも、円滑な受診および調剤が可能になります。
医師や薬剤師に見せて服薬状況を確認してもらうことで、薬ののみ合わせが適切かを確認することや重複投与を防ぐことができます。
- お薬手帳は常に携帯し、病院や薬局でご提示ください。
お薬はどのように保管したらいいの?
- お薬には、温度や湿度、光などの影響を受けやすいものがあります。医師・薬剤師等の指示もしくは、薬袋や説明書などに書かれている保管方法に従うことが大切です。
- 錠剤やカプセル剤を包装から出して保管することは避けてください。
- 特に指示がない場合は室温(1-30℃)での保管で構いませんが、直射日光の当たる場所や湿気の多いところ、温度変化の激しい場所での保管は避けましょう。
使わなくなったお薬はどうしたらいいの?
- 飲食物に賞味期限・消費期限があるのと同じようにお薬にも有効期限、使用期限があります。
- 古いお薬や、いつもらったのかわからないお薬は、「いつか必要になるかも…」とは考えずに必要がなくなった時点で処分しましょう。
- のんでいないお薬をおいておくと、間違ってのんでしまう原因にもなります。現在必要としているお薬だけを手元におくようにしてください。
よく似た症状の人にお薬をあげてもいいですか?
病院で処方されるお薬は、その人の症状や体質、年齢などに合わせた「その時のその人」専用のものです。「症状が似ているから」「よく効いたから」といって、家族間や友人間で共有するのは止めてください。効果がないばかりか、思わぬ副作用が出ることがあります。
医師が処方するお薬と市販のお薬はどう違うの?
- 医師が処方するお薬は1つの薬に1つの成分が入っているものが多く、患者さん一人ひとりの症状や体質に合わせて医師が種類や量を決めて処方しています。医師の指示通りに使用しましょう。
- 市販のお薬は1つの薬に色々な成分が入った総合的なお薬が多く、医師の処方するお薬に比べて含まれている量が少ないことが一般的です。購入される時にわからないことがある場合、不安なことがある場合は薬局の薬剤師などに相談しましょう。
服用(使用)中は車の運転をしてはいけない薬があるのはなぜ?
- 服用(使用)後に、車の運転の支障となるような眠気、注意力の低下、目のかすみやめまいなどを起こす薬があるからです。のみ薬だけでなく注射薬、貼り薬、目薬などでも起こることがあります。
- 眠気の出る薬を服用(使用)中に交通事故が報告されていますので、十分に注意して下さい。自分の判断で使用をやめたり量を調節したりせず、不安がある場合には必ず医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
錠剤が大きくてのみにくいので半分に割ってのんでもいい?
薬によっては、以下のような特徴があります。
- 腸で吸収させるために胃で溶けずに腸で溶けるように工夫してあるもの
- 効果が長く続くように工夫されたもの
- 苦みやにおいなどを防ぐように工夫されたもの
このような錠剤を割ったり、カプセルを外してのんだりすると、期待した効果が得られなかったり、時には効果が強く出すぎたり、副作用が出たりすることがあります。
したがって、自己判断で錠剤を割ったり、カプセルを外したりしないようにしましょう。どうしてものみにくいようでしたら、医師・薬剤師等にご相談されることをお勧めします。
水なしでのめるお薬って?チュアブル錠、OD錠、舌下錠の違いって?
- チュアブル錠
錠剤をかみ砕いて,唾液で溶かしてからのむお薬です。
用量の多いお薬に使われることが多く、一般的に大きい錠剤になっています。
水なしでのめますが噛み砕かなければ錠剤のまま口の中に残ってしまいます。
- OD錠(口腔内崩壊錠)
口の中で溶かしてのめるお薬です。
チュアブル錠と違って普通にお水でのむこともできます。
- 舌下錠
のみ込んだり、噛み砕いたりせずに舌の下に入れて溶かして使用するお薬です。
代表的なものに狭心症発作時に使うニトログリセリン錠などがあります。舌の下の粘膜は非常に吸収が速く、効果が出るまでの時間が短いのが特徴です。のみ込むと、お薬の効果が遅れたり、効かなくなったりします。